Since 2007/03/08
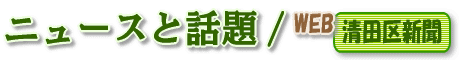

札幌・清田区革新懇(平和・民主・革新の日本をめざす清田区の会)の第4回総会は16日午後、清田区民センターで開かれ、加盟団体の年金者組合清田支部、新婦人清田支部、日本共産党の代表の人たちや個人など22人が参加しました。
総会は古田千代子新婦人清田支部事務局長の司会で始まり、代表世話人の吉岡ひろ子さん(共産党清田区市政相談室長)が開会あいさつしたあと、西区・手稲区革新懇事務室長の小笠原功氏が「いま革新懇とは」と題して革新懇の歴史や参院選後の情勢などについて講演しました。
河原亜雄事務局長が昨年度の活動と新年度の活動方針を提案、松崎均事務局員が会計報告をおこないました。
河原氏は毎月9日に行っている街頭宣伝・署名行動が12回にのぼり、後期高齢者医療制度反対の集会に向け老人クラブや町内の会長ら80人と対話したことなどの活動報告や、①「憲法をいかし九条を守り発展させる」の一点で清田区のあらゆる地域・学園・職場に「九条の会」が作られることをよびかける②社会保障や福祉の切り捨て、庶民増税・負担増に反対し、憲法を暮らしの中に生かす活動を進める③革新懇運動の輪を広げ、会員拡大に取り組む、などの方針を提案、承認されました。
総会は13人の世話人、10人の代表世話人、5人の事務局員を選出しました。

18日早朝、日本共産党清田区後援会と吉岡ひろ子党清田区市政相談室長は道銀清田支店前で街頭宣伝をおこないました。
吉岡さんは、4月4日に市田忠義書記局長を迎えて開かれる日本共産党演説会への参加を呼びかけました。そして参院予算委で小池晃議員が後期高齢者医療制度について「戦後を必死に働いてきたお年寄りに、『晩年になったら国から捨てられる』と感じさせる。こんな社会でいいのか」と追及したことが大きな共感を呼んでいると紹介、派遣労働などの非正規雇用の問題でも衆院予算委での志位委員長の質問が大反響を呼び、キャノンやロフトなどが直接雇用や正社員化に踏み切らざるを得ない状況を生み出したとのべ、札幌市でも党と市民の粘り強い運動で子どもの医療費無料化が就学前まで拡大したことなどにも触れて「党とみなさんが力をあわせれば政治も社会も変えることができます」と訴えました。
上田文雄札幌市長は18日の記者会見で「有料化について市民の理解は得られた」として「来年7月からの家庭ごみ有料化」を決定したとし、市議会に条例案を提出する考えを表明しました。
しかし「理解を得られた」という言い分には問題があります。市がおこなった「意識調査」は有料化の賛否を直接問うたものではありません。各区で開催された市民意見交換会では有料化への異論が相次いでいました。また清田区で開かれたタウントークでも、出席者から出された「有料化で減量というのは安易だ。名古屋では行政と住民が協力して減量に取り組んでいる」という意見を市長自身が聞いていました。
こうしたやり方で有料化をはかるのは、将来に禍根を残すものといわざるを得ないでしょう。

北野東部地域で活動する日本共産党北野台支部と後援会は14日、「どうなる?くらしと医療―吉岡ひろ子と語る会」を開きました。
このつどいには10人が参加、吉岡ひろ子党清田区市政相談室長が国政と地方政治の問題を解決する政策と日本の未来像をお話し、懇談しました。
障がいをもつ人の参加もあり、おもに医療と福祉、後期高齢者医療制度などについて語り合いました。
このつどい後、参加された人が「しんぶん赤旗」日刊紙の購読を約束してくれたことにつながり、日本共産党北野台支部は確信を深めています。
●市議会予算特別委で11日、宮川潤議員の質問への答弁で保健医療担当部長は「小学校卒業まで入院医療費を助成する」と答弁しました。また保健福祉局長は保険証取り上げによる医療抑制(62分の1)があることを認めました。
●市議会予算特別委で11日、井上ひさ子議員の質問への生活衛生担当部長の答弁で、札幌市が新年度から輸入加工食品の残留農薬検査を行うことが明らかになりました。
●市議会予算特別委で11日、伊藤りち子議員は、家庭ごみ有料化問題で市が有料化の賛否も聞かず「おおむね理解が得られた」としていることを批判。環境局長は「有料化だけの賛否を聞くと有料化の負担だけに目が向けられる」と弁解、伊藤議員は「賛否も聞かず合意を得られたと無理やり結論を出している」と指摘、有料化せずに減量をすすめるべきと迫りました。
●市議会予算特別委での坂本恭子議員の質問に、市は選管委員は通常は20〜30分の会議が年間15回程度ということを明らかに。坂本議員は委員報酬の見直しを求めましたが市側は「他の政令市と比較して高すぎるとは思わない」と居直りました。
●日本共産党札幌市議団は17日、「木の城たいせつ」の破産にともなう関連倒産防止と雇用対策について上田文雄市長に申し入れをおこないました。セーフティーネット保証制度の認定、セーフティネット貸付のスムーズな実行などを国や道に働きかけること、市としての利子補給や、従業員や住宅購入者の相談窓口を設けることなどを求めました。
生活保護費の不正受給は許されない。滝川市での事例はあまりにもひどい。関係者が放置した結果だ。市長が責任を取ると表明しているが当然だ▼生活に困窮し、電気、ガスが止められたあげく「餓死」にいたる例が北九州、函館などで発生した。これも行政の怠慢だがあまりにも対照的だ▼保護措置は税金であり公平でなければならぬ。正反対にみえるこれらは行政の現場に問題が潜んでいることのメダルの裏表だ▼老齢加算と母子加算の減額・廃止、保護基準も改悪へ…。「行革」と国の政策としめつけが現場のモラルを低下させたのではないか。ならば一層現場では公務員としての誇りと使命感を発揮してほしいと思う。(岩)
「清田区新聞」08年03月23日付より